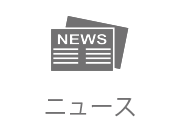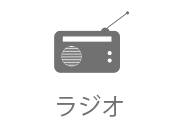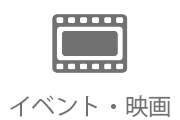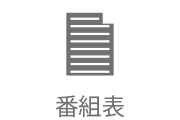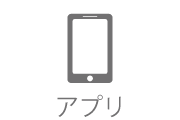鶴岡です。
今日、9時台には、わらべ歌「おてらのおしょうさん」についてお送りしました。
私が知っているわらべ歌「おてらのおしょうさん」は、
おてらのおしょうさんが、かぼちゃの種を蒔きました。
芽が出てふくらんで、
花が咲いたらジャンケンポン!
です。
ちゃんと手遊びもあって、
芽が出て→手のひらを胸の前で合わせる
ふくらんで→指を曲げてふくらませる
花が咲いたら→指を開いて花の形をつくる
ジャンケンポン→ぐるぐる腕を回して ジャンケンをする
というものでした。
こどもの遊びは、ジャンケンで始まることが多いので、きっと日常のジャンケンソングとして私も、毎日のように、歌っていたと思います。この「おてらのおしょうさん」は、昭和50年に出されたレコードにも、手遊び解説付きで歌が入っています。
ところが、平成の「おてらのおしょうさん」は、
お寺のおしょうさんが、かぼちゃの種を蒔きました。
芽が出てふくらんで、花が咲いたら.........この次が
枯れちゃって、
忍法使って空飛んで、
救急車に運ばれて、
ぐるぐるまわってジャンケンポン!
と、おしょうさんは大変なことになっていました。
これ、ある一部地域で歌われているものなのか?というと、そうではありません。ちゃんとCDにもなっています。タイトルは「おてらのおしょうさん(平成版)」。
昭和の「おてらのおしょうさん」は、花が咲いたらジャンケンできますが、時が平成になると、咲いた花がいったん枯れちゃうんですね。
こうした進化する「おてらのおしょうさん」について、お寺の和尚さんに、実際にお話をうかがいました。秋田市土崎、曹洞宗蒼龍寺(そうりゅうじ)のご住職、佐藤堅明(けんみょう)さんです。
「途中でしぼんだお花も、実がなってしぼんだはず。その実もまた地面に落ちれば、新しく芽が出て花が咲く、という、命が繰り返される。そう言うことがまわっているという風に考えられるのではないか。」
なるほど。そう考えると、枯れてしまう花は、必ずしも残念なことではないかもしれないと思えるようになります。
さらに、ご住職は、
「今、なかなか難しい問題が多い世の中だが、止まない雨はないという話もされる。地球は回って時間が進んでいる。どんどん良い時代に、良い世の中になるように。子ども達が希望を持ちながら暮らせるような世の中を、私たち大人が築いていけたら素晴らしいかなと思う」
とまとめて下さいました。
RN ほじなしbabyさんは、「子どもの想像力って凄いっすね!!」とメールを下さいました。
子ども達は、その時代、時代をよみながら。あるいは、「こうあったらいいな」という願いをこめながらわらべ歌の歌詞に映し出し、進化させているのかもしれませんね。
); ?>)
); ?>)