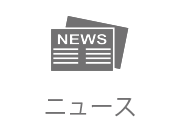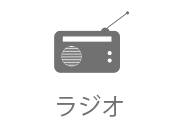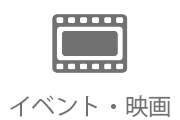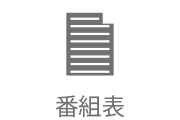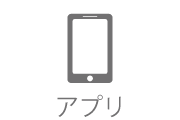2011年2月4日(金)
賀内です。
きのうの「秘密のケンミンSHOW」で、秋田県南部の食習慣として「炊き込みご飯に砂糖を入れる」というのが放送されていました。
県南全部というわけではないようですが、甘みを強調した味付けになっている地域は、ありますね。私も県南に親類がいるのでわかります。
で、一夜明けた今朝の「あさ採りワイド」には、その感想、体験、さまざまいただきました。
大仙市の「ペコちゃんのママ」からは、
「私の実家は甘党に加え、甘いのが美味いという感覚で、なんでも甘いです。麦茶や梅干しにも。トマトにはグラニュー糖。それに輪をかけるのが叔母の嫁ぎ先。カレーや納豆などにも大量にかけて食べます」
三種町の「カーネーション」さんからは、
「私の義母も甘党でした。炊き込みご飯に砂糖や、栗の甘露煮のつゆを使ってました。ポテトサラダも茶碗むしも、玉子焼きも、とっても甘かったです。そういう祖母の味に慣れ親しんだ娘が東京生活でびっくりしたことは、炊き込みご飯も茶碗むしも玉子焼きも甘くないということでした」
「ガックン・ママ」さんは、
「39年前、夫の実家で炊き込みご飯を作ったら、みんな無言になってしまいました。あとで聞いたら『甘くなかったから』で二度びっくり!!炊き込みご飯にお砂糖なんて、東京育ちの私には考えられませんでした。でも食べてみたら砂糖入りのほうが私もおいしいと思い、今では炊き込みご飯はもちろん、茶碗むしも甘いのがわが家の味になっています」
砂糖が貴重品だった時代は、甘いのがイコールぜいたくなことだったという、その名残りなのでしょうね。ただ、それならどこでも甘くなるはずですが、地域によって違うというのが興味深いところです。
今は減塩運動もそうですし、肥満や生活習慣病を防ぐために砂糖の使用量を減らしていて、薄味が世の流れです。
でもそれだけに、舌にじーんとくるような強い甘さは、ふるさとでなじんだ、忘れられない味なのでしょうね。体に悪いと言われようが、なんだろうが。
きょうの反響の大きさに驚くと同時に、「ふるさとの味」の大切さに思い至ったのでした。
); ?>)
); ?>)