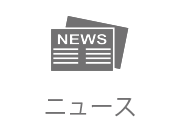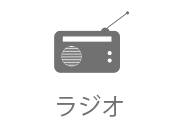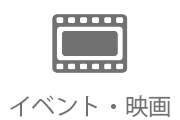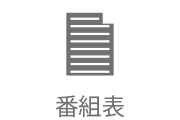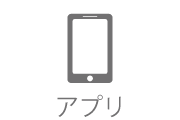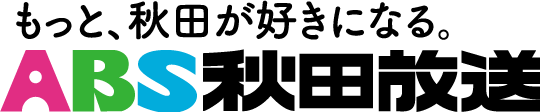番組審議会リポート|
PROGRAM COUNCIL REPORT
第660回番組審議会が6月16日に開かれました。合評番組は「日本のチカラ #421 マリさんのいぶりがっこ ~大好きな味を いつまでも~」でした。
委員からは
この番組の主人公の加藤マリさんは、いぶりがっこ作りだけではなく、スキーのコーチ、ホテル経営、子育て、犬の世話と、何足ものわらじをはいて大変そうなのに、常に笑顔で楽しそうだ。見終わって「頑張ろう」という気持ちになれる、メッセージ性の強い番組だった。
漬物文化が盛んな秋田の中でも、いぶりがっこは全国的な人気商品となっている。しかし、高齢化と食品衛生法の改正で、昔ながらの味を受け継いできた年配の人たちが作りにくくなっている中、若い人がそれを受け継いでくれるというのはありがたいことだと感じた。ただ、「いぶりがっこの伝統を守ろうと奮闘する女性農家の物語」というナレーションあったが、ここに「女性」はいるだろうか。「男性農家」という表現はしないと思うので、そこが少し気になった。
主人公のマリさんも、加藤家の方々もみなさん明るくて、前向きないい番組だった。しかし、現実問題として高齢者の作り手がお金をかけて法律に則った加工所を作ることはできないし、それをマリさんが作ってみんなで使っている、という状況を、どうやって成立させたのかを具体的に示して欲しかった。そうすることで、より、いぶりがっこの伝統は守られていくだろう、ということを確信できたと思う。
多額の投資をして作った作業所を、共同作業所として今まで何十年もいぶりがっこを作ってきたレジェンドのような方たちに使ってもらう、というのは素晴らしいことだと思った。マリさんとお年寄りたちが、できあがったいぶりがっこを試食しながら笑いあうシーンで番組が終わっていたのも良かった。すがすがしさが心に残った。
大根を栽培し、加工し、自ら販売する、といういわゆる6次産業ともいうべきものが見事に成立していた。昨今は後継者がいないことから衰退していく農業産地も多く見られるが、マリさんの事業はそうした現場にとって参考になるものなのではないか。
この番組には、明るく前向きなマリさんの日常の陰に色々な問題が埋め込まれている、と感じた。一例を挙げれば、食品衛生法の改正は果たして妥当なものだったのか、それによって消えていく地域の伝統について政治や行政はどう向き合うのか、という問題もはらんでいる。ひとつの番組で何もかも語りつくすことは難しいかもれないが、そこに収まりきらない疑問が湧いてきた。それがこの番組の持っている深さであり力なのかもしれないが、番組としてまとめていくことの難しさも併せて感じた。
といった意見が上がりました。
第659回番組審議会が5月29日に開かれました。合評番組は「ABS news every.+ 消えゆく県魚~ハタハタを追う~」でした。
委員からは
ハタハタが少なくなっている、というのは度々聞くことだったが、ここ数年で急激に減っていることを番組を通して確認した。地球全体の温暖化が止められない中でどうやって現実に折り合いをつけていくのか。漁師が減ってきている中で秋田の漁業をつなぐためにどうしたらいいのか、という部分にも触れて欲しかった。
タイトルになっている「県魚(ケンギョ)」という言葉だが、県に問い合わせたところハタハタについては「県の魚(サカナ)」と呼んでいるとのことだった。
映像を通じて、ハタハタが取れないことによる漁師たちのいら立ちや焦り、あきらめも混じったような何とも言えない様子が伝わってきた。ハタハタという魚が特別な魚なんだということが良く分かった。番組の終わりに一人の漁師が言った「ハタハタの生命力に懸けるしかない」という一言が、祈るような思いやハタハタへの愛情を表現していて、とても感慨深かった。
ハタハタの漁獲量が減る理由として「レジームシフト・生態系の構造転換」というものが挙げられていた。これに対応して資源量を増やすために禁漁期間が設けられた、ということだったが、これが現在の話ではなく過去の話だったことで、取れなくなった理由と時間軸が行ったり来たりしている印象があった。録画を繰り返し見ることで理解できたが、1回しか見ていない人はどう感じたのだろうか。
番組を見ていて、漁師の気持を考えると心が苦しくなってきた。冒頭で、家にやってきたなまはげのお膳にハタハタが出ていたり、子供がおいしそうに食べている映像から、ハタハタが愛されている存在なのが伝わってきた。そのハタハタが激減している。「来年はきっと来るはず、大丈夫」と自分に言い聞かせるように語る漁師の一言に胸が痛くなった。漁師という仕事に対する明るい展望や対策といったものも示してほしかった。
ハタハタの漁獲状況をグラフで表したり、日本海側の各県の対策を地図に落とし込んだりといった、見せる工夫がされていて良かった。
昨シーズンの総漁獲量93トンに対して今シーズンが2トンという、驚くような激減ぶりが生々しく強烈に伝わってきた。この状況にどう対応すればいいのか、多くの人に真剣に考えてもらうためには、下手に明るい希望で終わらなかったことが良かったのかもしれない。今後行われるそうした議論に応えるためにも、この問題には継続的に取り組んでいって欲しい。
といった意見が上がりました。
第658回番組審議会が4月22日に開かれました。合評番組は「ABSラジオスペシャル マタギの森」でした。
委員からは
狩猟の季節、マタギはただ山におもむろに入って銃でバンバンと獲物を撃つのではなくその前に儀式があって、神社にお参りに行き、山に入る時に植物の枝葉をいぶしその枝葉で全身を清める、それでけがれを払うことになり魔よけの効力になる、など、今回ラジオを聴いて初めて知ることができた。
自然の中の鳥の鳴き声や、マタギの伝統的な道具を作る鍛冶屋さんの音など、各場面の音がとてもきれいに聞こえていた。音だけでも映像が浮かんでくるようだった。地域に伝わる番楽では子供たちのインタビューなどもあり、昔ながらの営みが続いていることが伝わってきた。
近年問題となっているクマの生活空間への出没とそれに伴う有害駆除が、本来のマタギの精神とは全く異なる作業であり嫌だ、駆除のために鉄砲を持ったわけではない、というマタギの人たちの気持が語られていた。襲われてケガをした人も登場していた。駆除に携わっている方たちの負担というものを軽々しく考えてはいけない、と感じた。
「マタギの森」というタイトルにふさわしく、森の音が素晴らしい作品だった。常に新しい場面の前には森の音が入っていて、季節を感じさせてくれた。言葉によらず表現されているものがたくさんあった。ただ、鍛冶職人の場面は仕事ぶりを見たことがないので想像することができず、映像が見たいな、という気持ちになった。こんな動作をしている、などの説明があったほうが良かったのではないか。
マタギをテーマにしたラジオの1時間番組、ということで最後まで聞き通すのは大変ではないか、と思っていたが、臨場感のある音や、有害駆除とマタギ文化の違い、そしてマタギの生活ぶりや思いなどが紡がれていて、あっという間の1時間だった。秋田県のクマの有害駆除に関する基本的な考え方というものに、山からの授かりものをいただく、というマタギの伝統が参考になるのではないか、と感じた。
マタギの人たちは言葉の訛りが強く,言っていることがわかりにくい場面がいくつもあった。しかし、近くにクマがいるかもしれない場所でマタギ同士が声を潜めて何かを話し合っている場面、これは何を言っているのかわからなくてもいいのではないか、と思ってしまった。臨場感、リアリティという観点からすると、あの緊迫した空気さえ伝わればいい。もしかしたら、何を言っているかわからないリアルさがより想像を掻き立てる、というラジオの新たな可能性が秘められていたのではないか。
といった意見が上がりました。
); ?>)
); ?>)